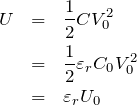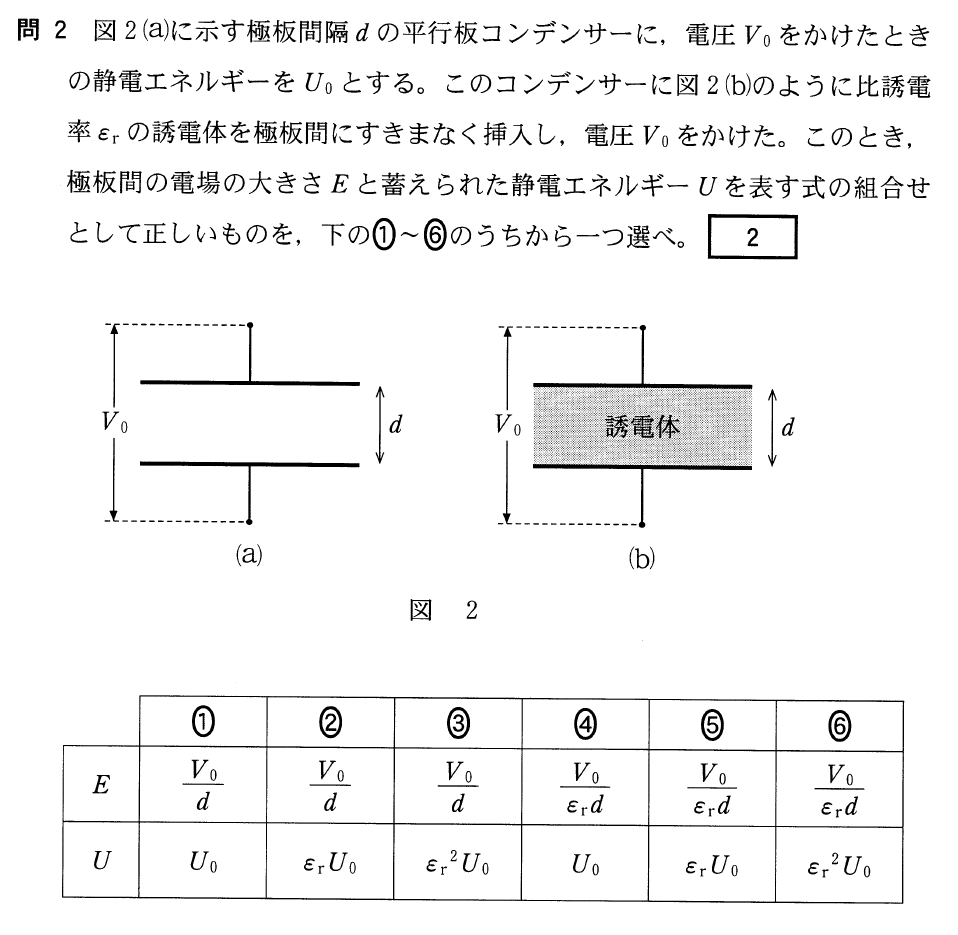
![]()
![]()
![]() )があったとして、極板間に誘電率
)があったとして、極板間に誘電率![]() 、比誘電率
、比誘電率![]() の誘電体をすき間なく挿入すると、電気容量は
の誘電体をすき間なく挿入すると、電気容量は
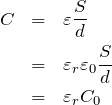
![]() 倍になるっていうことなんだ。
倍になるっていうことなんだ。
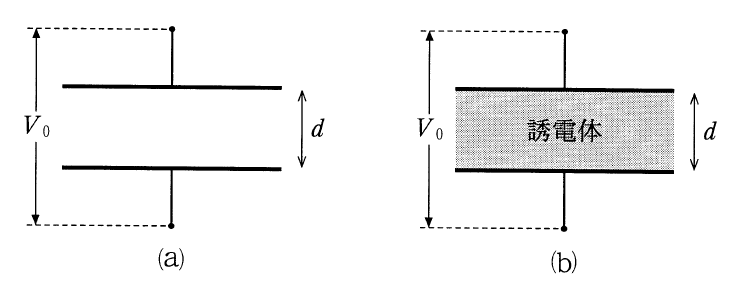
![]() とすると、(b)の電気容量は
とすると、(b)の電気容量は![]() となるっていうことだ。
となるっていうことだ。
![]()
![]()
![]()
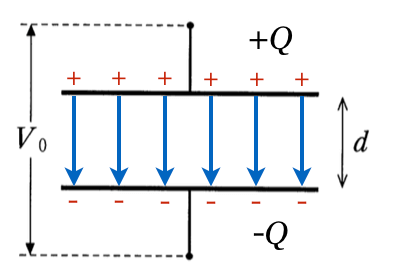
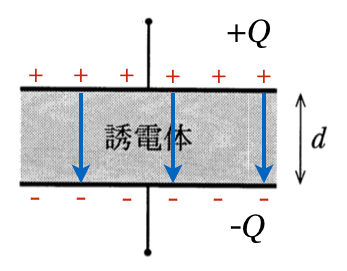
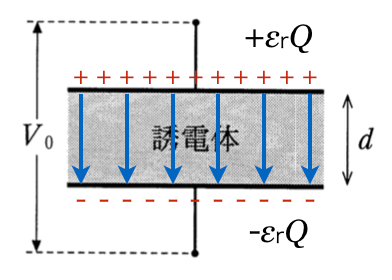
![]() と組み合わせて、いくつかの式があるのよね。
と組み合わせて、いくつかの式があるのよね。
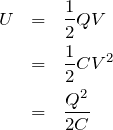
![]() 倍になるということなので、
倍になるということなので、
![]() ね。
ね。
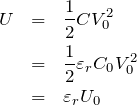
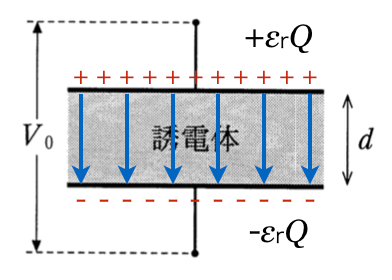 センター試験の問題で「物理」を学ぼう!
センター試験の問題で「物理」を学ぼう!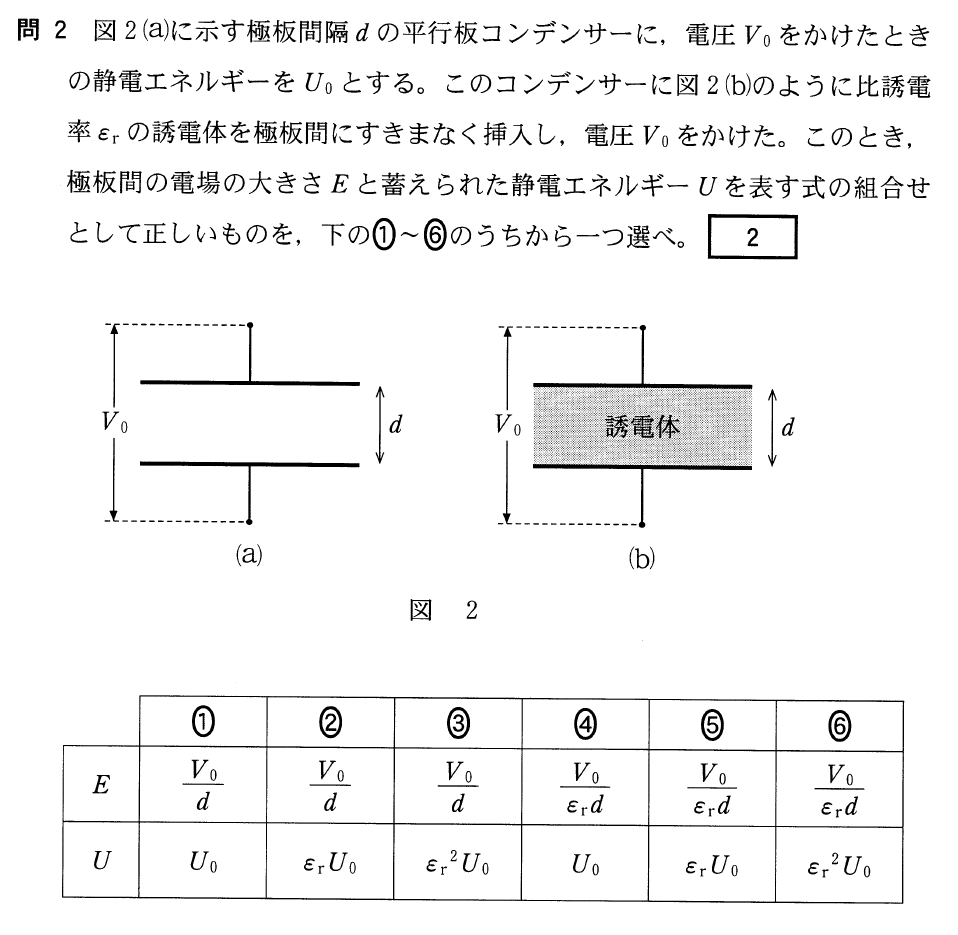
![]()
![]()
![]() )があったとして、極板間に誘電率
)があったとして、極板間に誘電率![]() 、比誘電率
、比誘電率![]() の誘電体をすき間なく挿入すると、電気容量は
の誘電体をすき間なく挿入すると、電気容量は
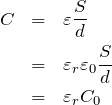
![]() 倍になるっていうことなんだ。
倍になるっていうことなんだ。
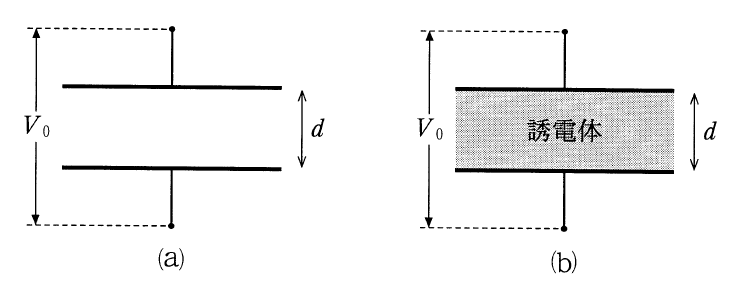
![]() とすると、(b)の電気容量は
とすると、(b)の電気容量は![]() となるっていうことだ。
となるっていうことだ。
![]()
![]()
![]()
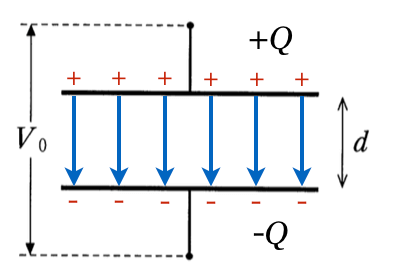
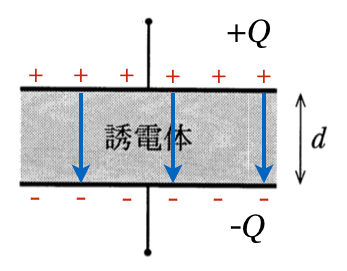
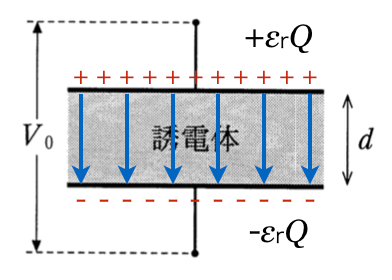
![]() と組み合わせて、いくつかの式があるのよね。
と組み合わせて、いくつかの式があるのよね。
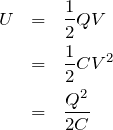
![]() 倍になるということなので、
倍になるということなので、
![]() ね。
ね。