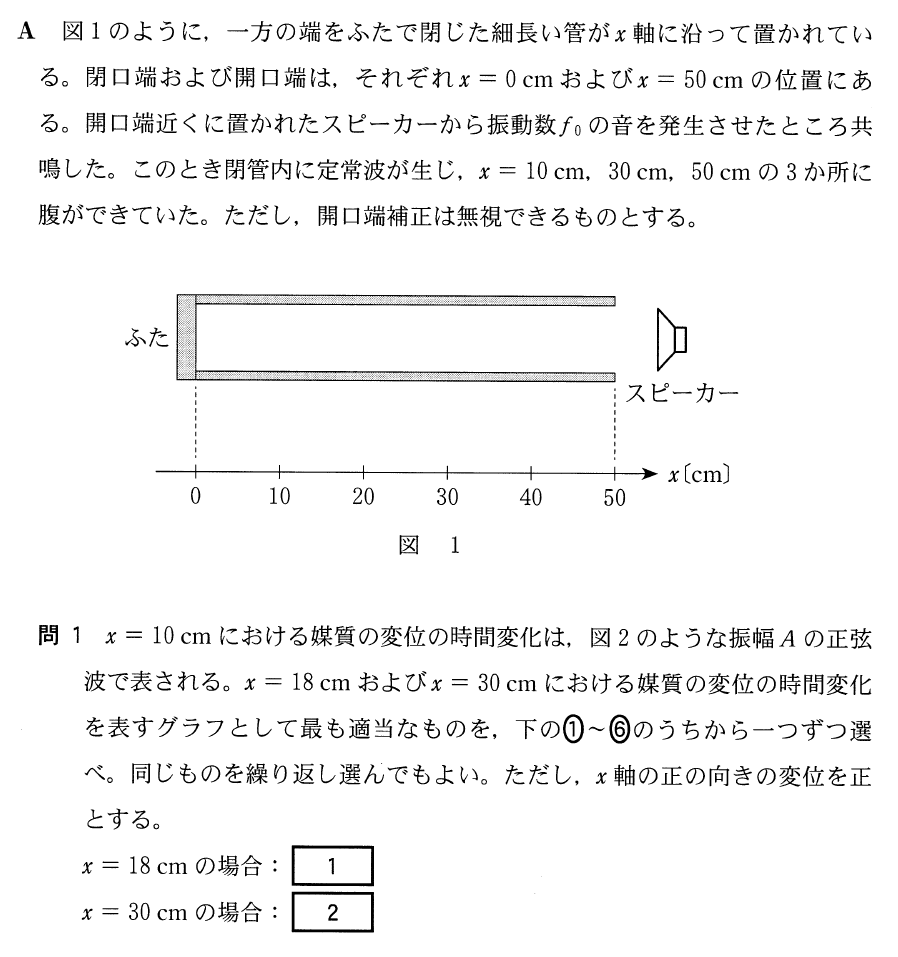
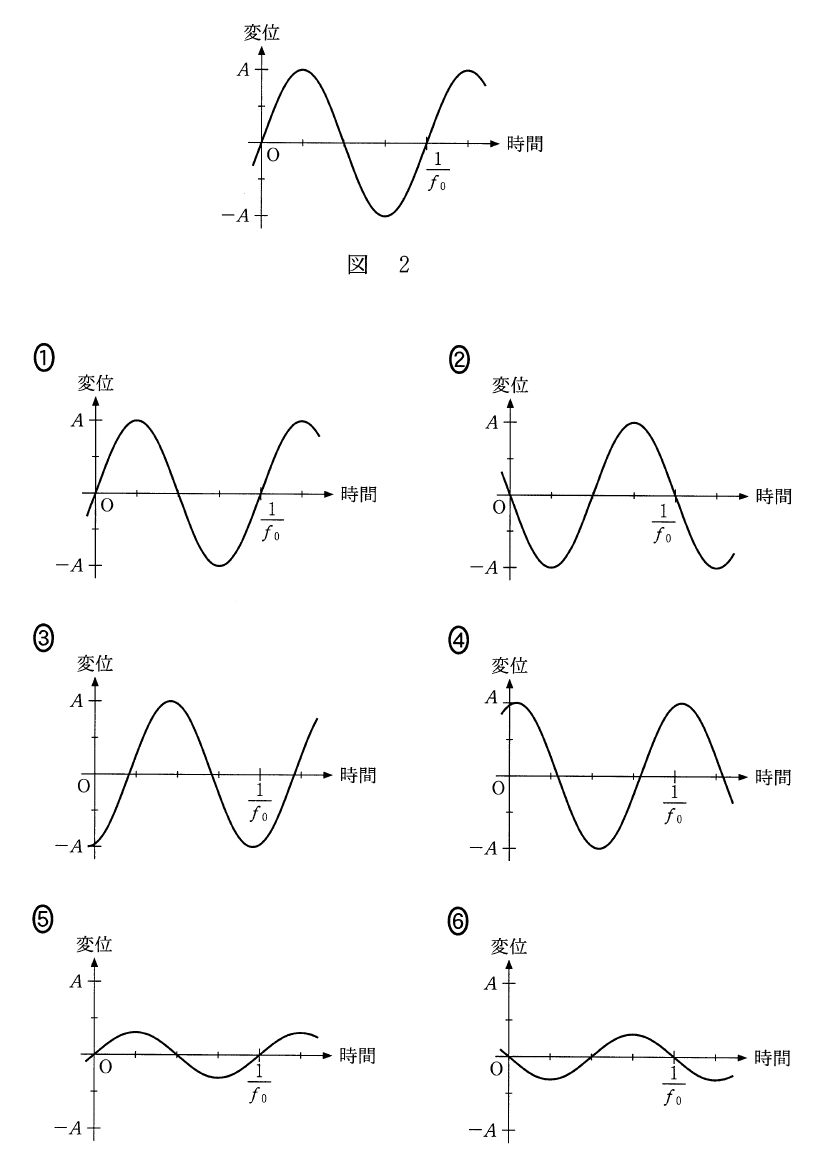
まずは、

10cm、30cm、50cmの3カ所に腹ができている図を描こうか。

0cmの所は閉口端なので、節になるような図ね。
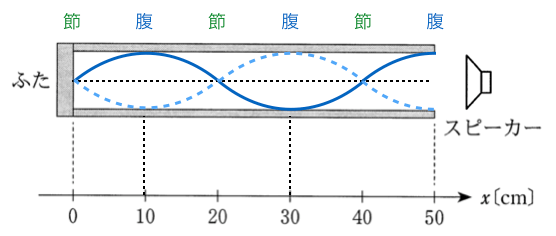
いいね。

10cmの所の媒質はどう動く?
そこが良く分からないんだけど、確か管の中では定常波ができているのよね。定常波って動かないんじゃなかったっけ?だから、「常に定まった波」って書くんでしょ。
確かに定常波は動かないように見えるね。だけど何も動いていなかったら、「波」でもないんじゃない?
そうか、媒質は動いているのか。波としては動いていないけど、媒質は動いているのね。
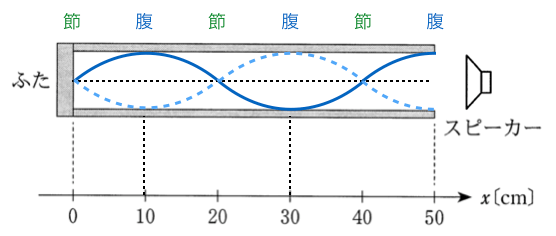
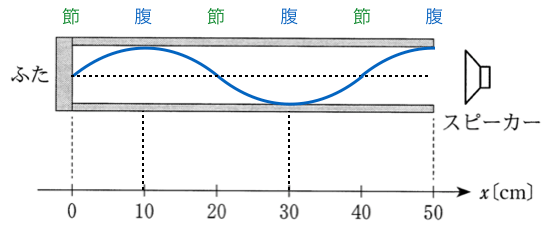
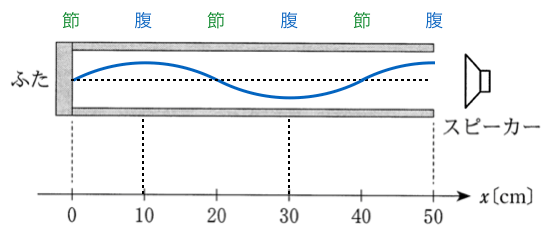
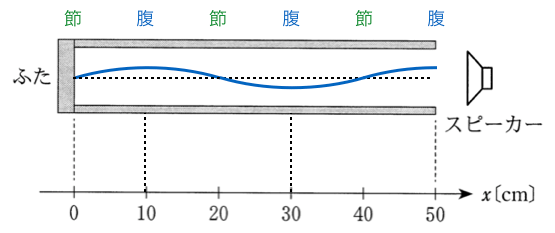
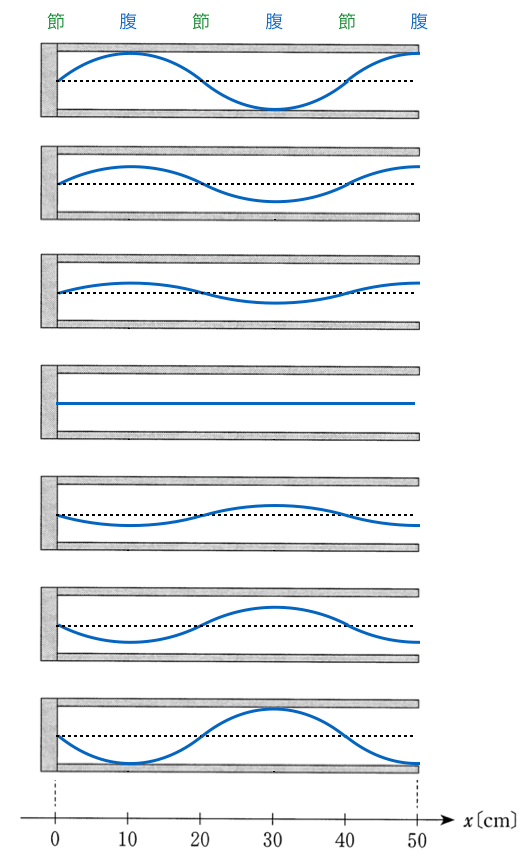
そういうことね。このあとは、逆に変化して元に戻る、っていうのを繰り返しているのね。
そうだね。あと一応確認だけど、この波の書き方を横波表示って言うんだけど、実際の音は縦波なのでそこは間違えないでね。
そこは大丈夫。この図では媒質は上下方向に変位しているように描いてあるけど、実際は左右方向に変位しているっていうことでしょ。
そういうことだ。じゃあ、問題に戻ろうか。グラフを選ぶ問題だったね。
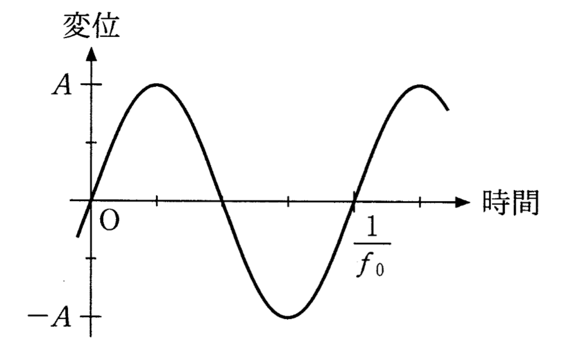
このグラフって、

10cmの媒質の時間変化ということだけど、さっきの図だと変位が最大から始まってるわよね。
さっきの図はそうだね。最初の図が

0とは限らないよね。このグラフに合わせて図を並べてみると、
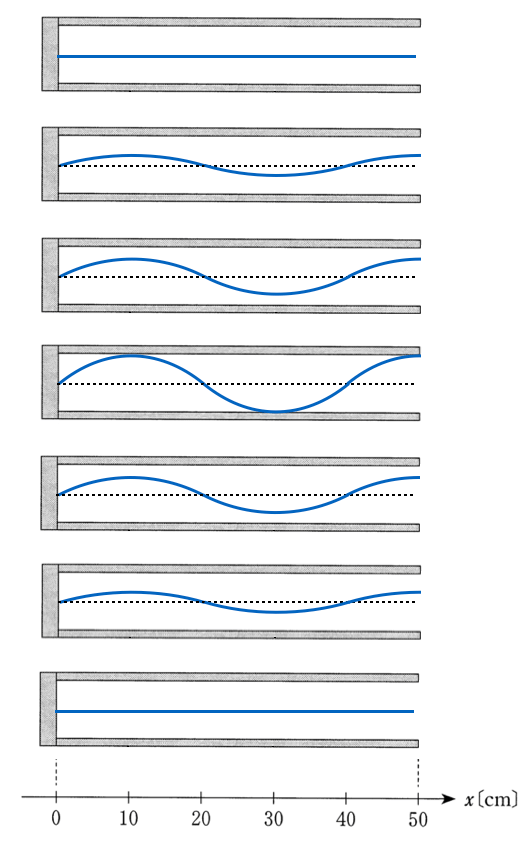
そういうことね。

10cmの変位を表してみると、こんな感じかな?
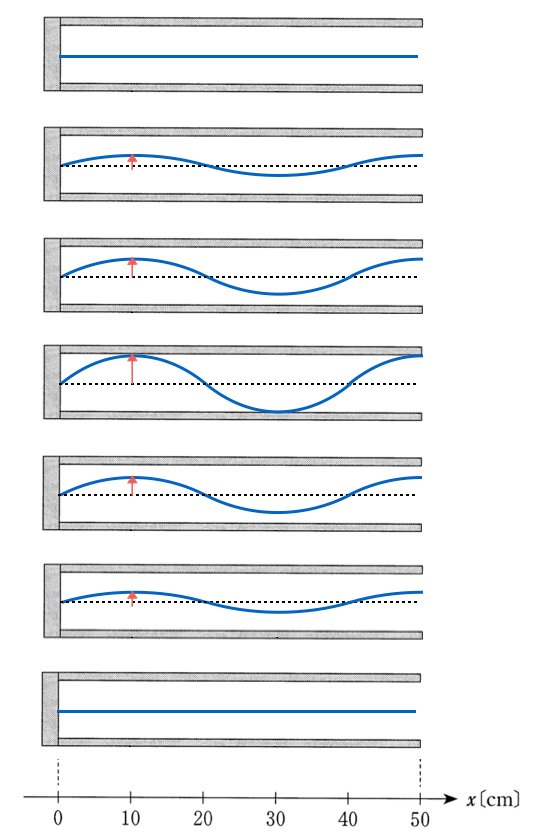
これで半周期だね。ついでに

18cmと30cmを描いちゃえば。
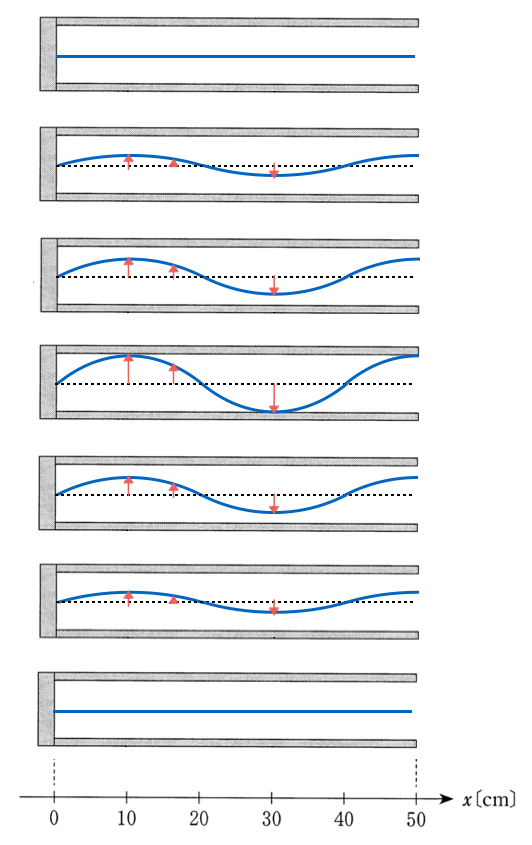

18cmは変位が小さいわね。山になったり谷になったりするタイミングは

10cmと同じだから、グラフは⑤ね。
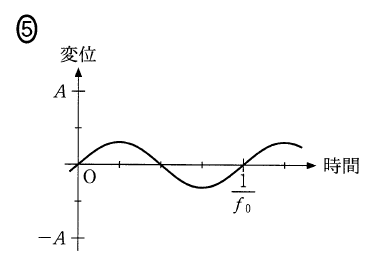
タイミングが同じっていうのは、「位相が同じ」って言うんだ。
聞いたことがあるわ。じゃあ、

30cmは変位は同じだけど位相が逆っていうことね。グラフは②ね。
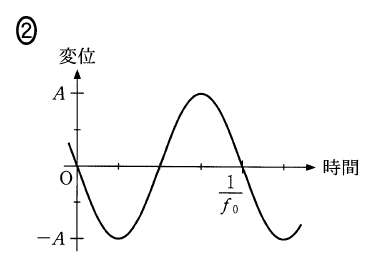
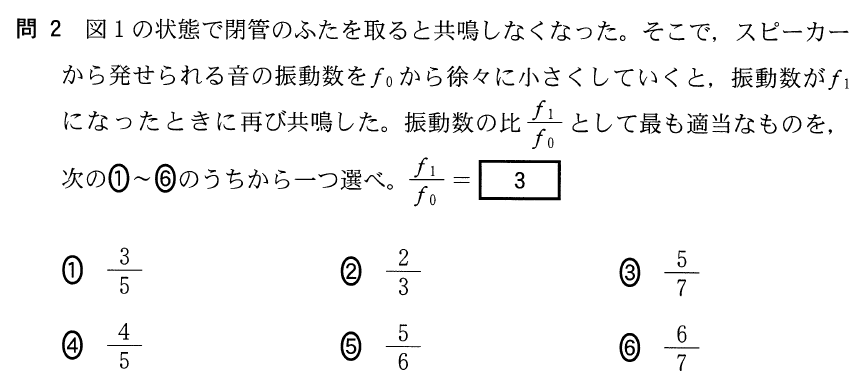
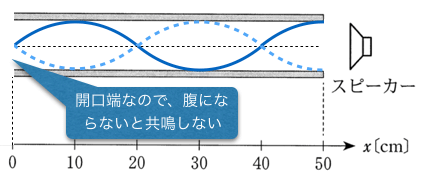
振動数を小さくした、とあるけどこの図で考えると、何が変わるのかな?

で、音速

は変わらないから、振動数

が小さくなると、波長

が大きくなるね。
波長が徐々に長くなった結果、共鳴したときの図はどうなるかな?
ふたがあった方の開口端も腹になればいいのよね。こんな感じかな。
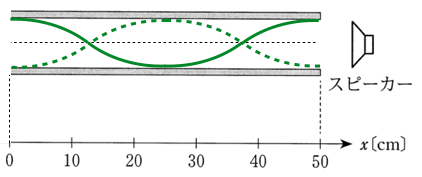
その通りだね。準備はこれでできたので、ここからどうしよう。
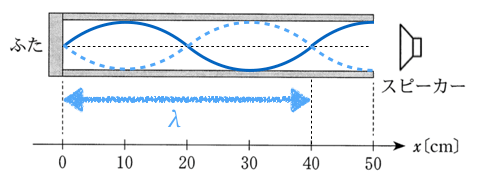
ふたが付いているときの波長は、図より

40cmと分かるわね。ふたをはずすと、
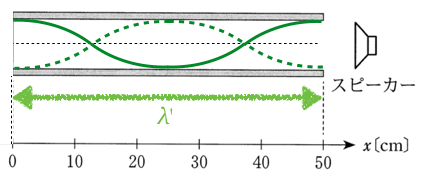
図から波長は

50cmとなるわ。
音速を

として、

に代入すると、
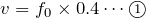
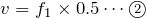
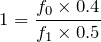

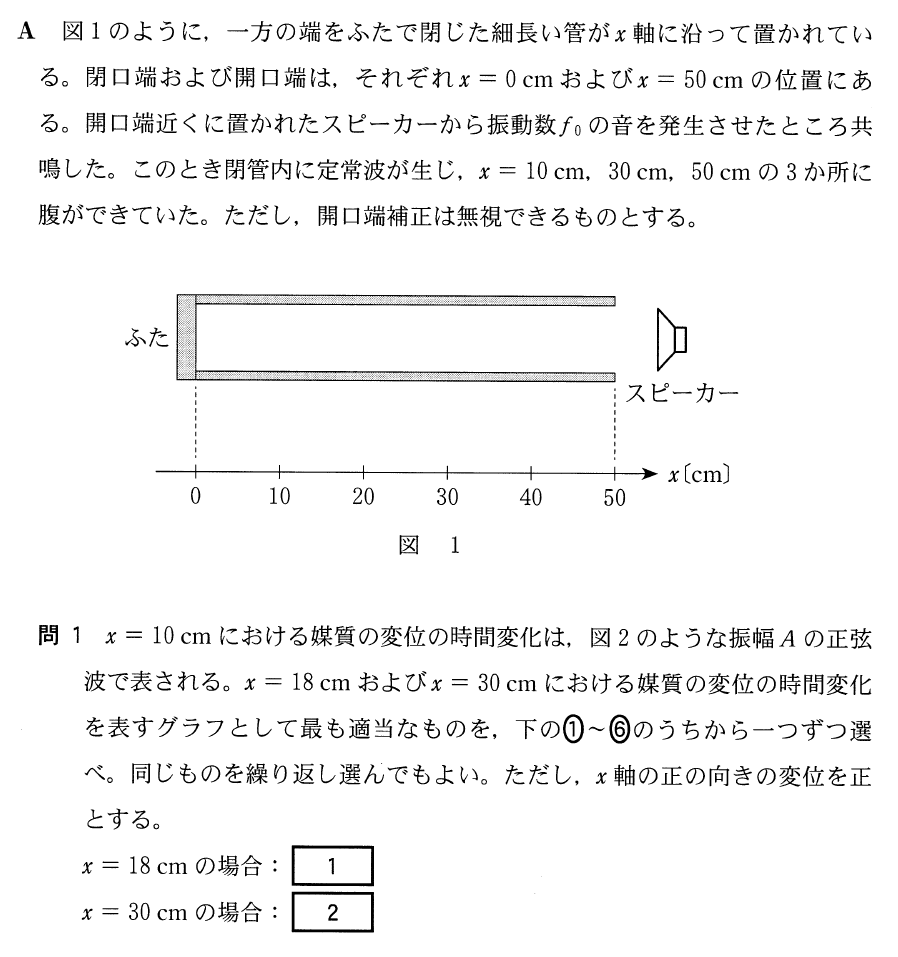
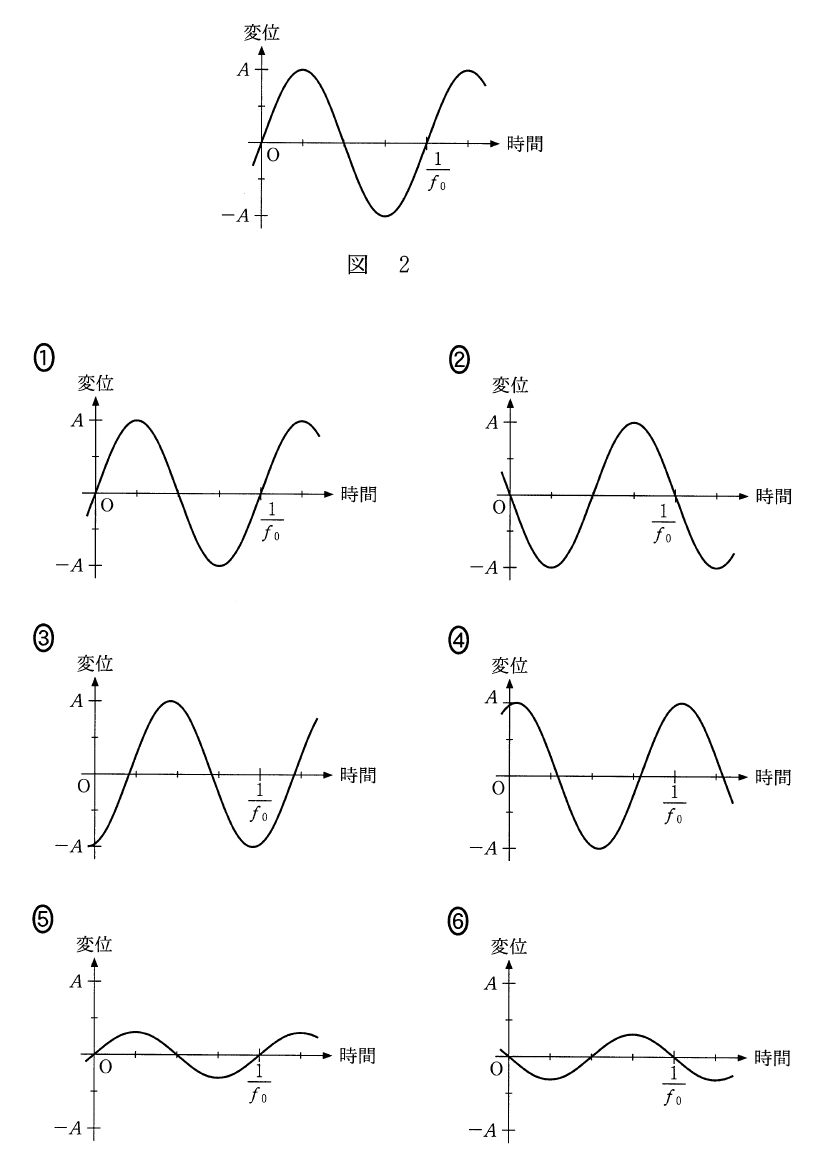
![]() 10cm、30cm、50cmの3カ所に腹ができている図を描こうか。
10cm、30cm、50cmの3カ所に腹ができている図を描こうか。![]() 0cmの所は閉口端なので、節になるような図ね。
0cmの所は閉口端なので、節になるような図ね。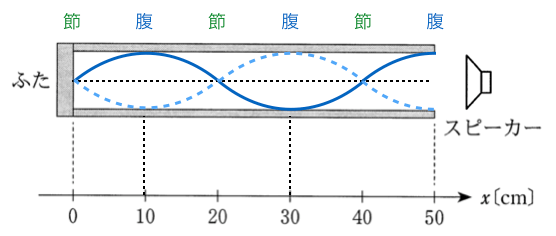
![]() 10cmの所の媒質はどう動く?
10cmの所の媒質はどう動く?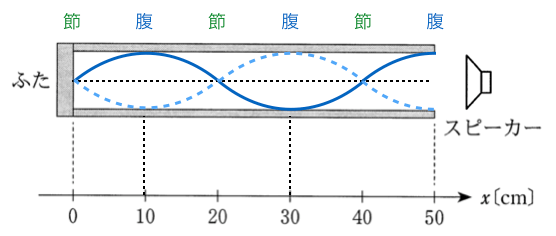
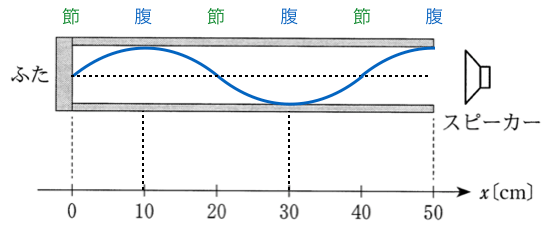
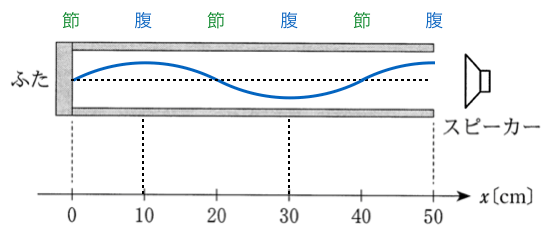
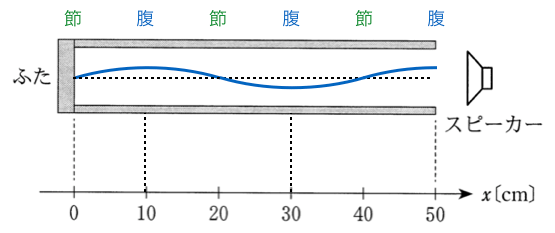
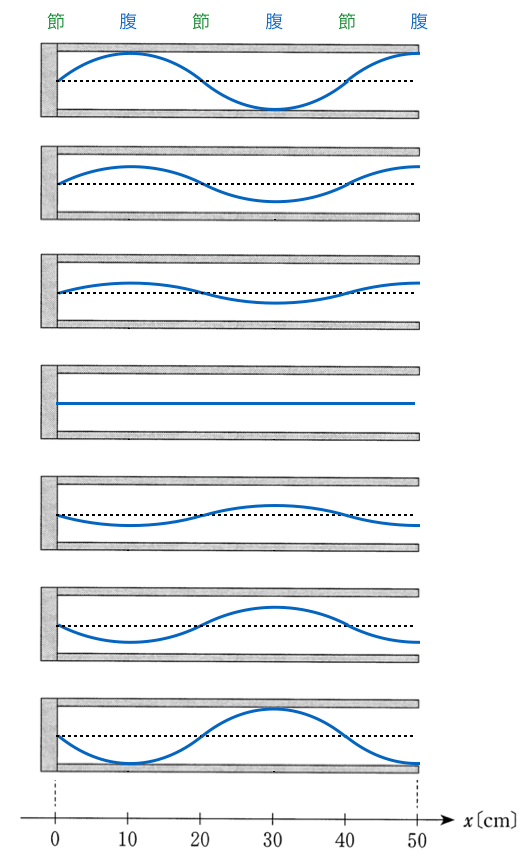
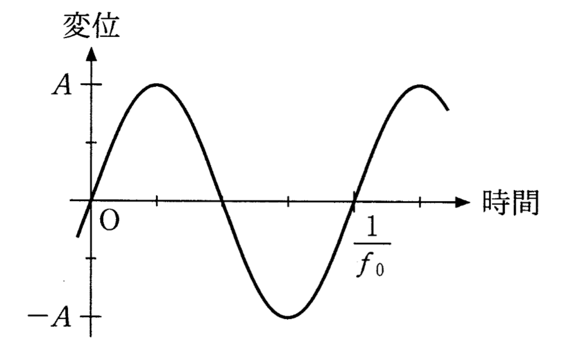
![]() 10cmの媒質の時間変化ということだけど、さっきの図だと変位が最大から始まってるわよね。
10cmの媒質の時間変化ということだけど、さっきの図だと変位が最大から始まってるわよね。![]() 0とは限らないよね。このグラフに合わせて図を並べてみると、
0とは限らないよね。このグラフに合わせて図を並べてみると、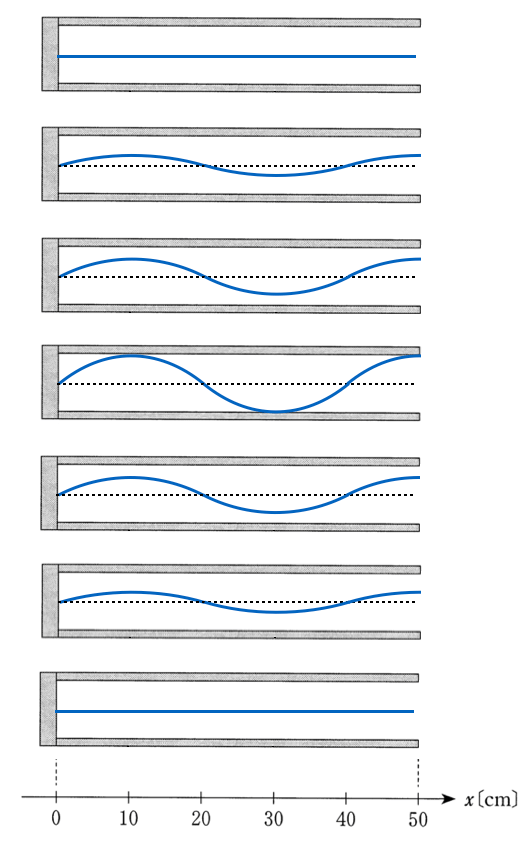
![]() 10cmの変位を表してみると、こんな感じかな?
10cmの変位を表してみると、こんな感じかな?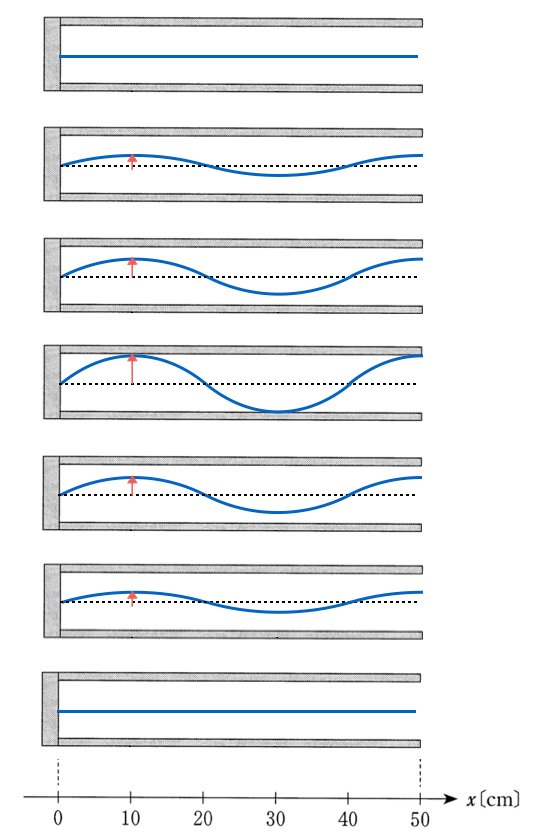
![]() 18cmと30cmを描いちゃえば。
18cmと30cmを描いちゃえば。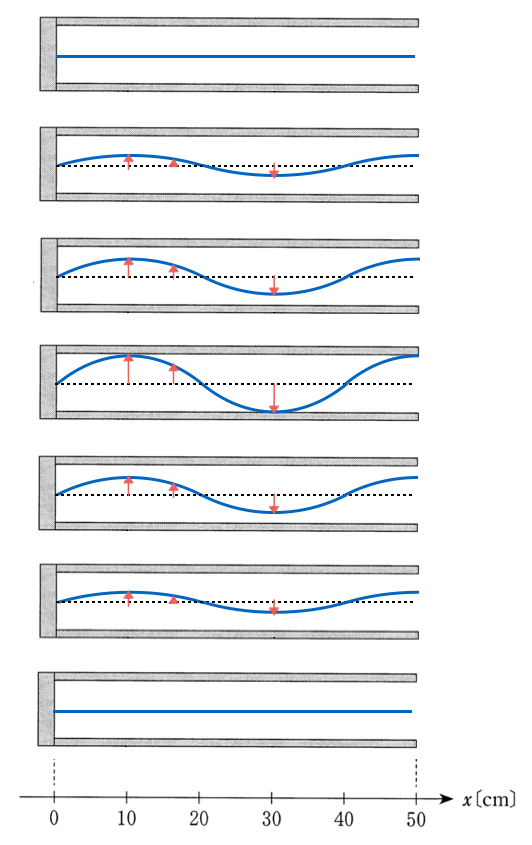
![]() 18cmは変位が小さいわね。山になったり谷になったりするタイミングは
18cmは変位が小さいわね。山になったり谷になったりするタイミングは![]() 10cmと同じだから、グラフは⑤ね。
10cmと同じだから、グラフは⑤ね。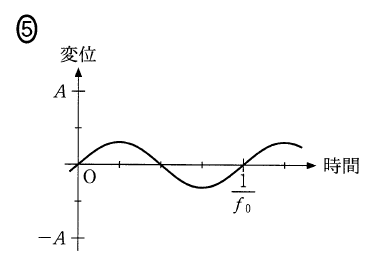
![]() 30cmは変位は同じだけど位相が逆っていうことね。グラフは②ね。
30cmは変位は同じだけど位相が逆っていうことね。グラフは②ね。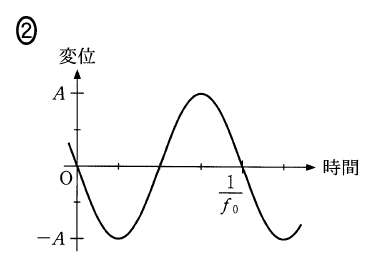
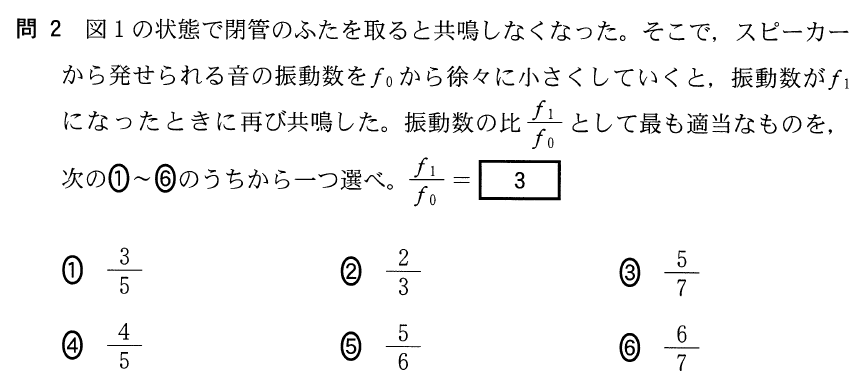
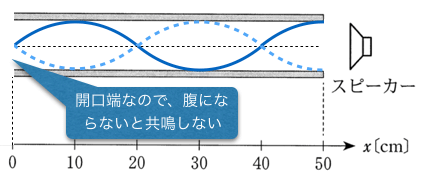
![]() で、音速
で、音速![]() は変わらないから、振動数
は変わらないから、振動数![]() が小さくなると、波長
が小さくなると、波長![]() が大きくなるね。
が大きくなるね。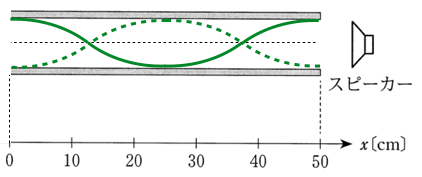
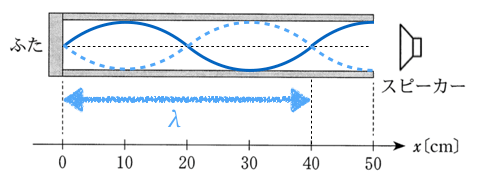
![]() 40cmと分かるわね。ふたをはずすと、
40cmと分かるわね。ふたをはずすと、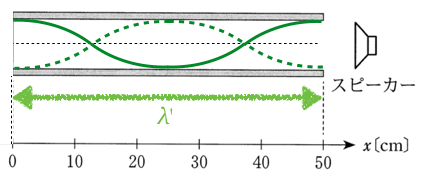
![]() 50cmとなるわ。
50cmとなるわ。![]() として、
として、![]() に代入すると、
に代入すると、![]()
![]()
![]()
![]()

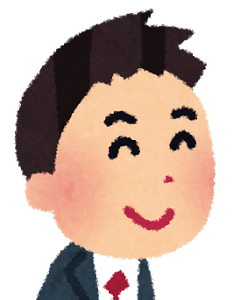
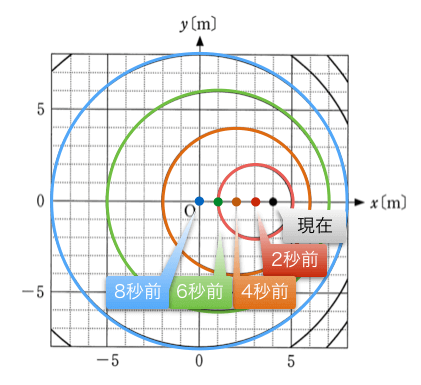
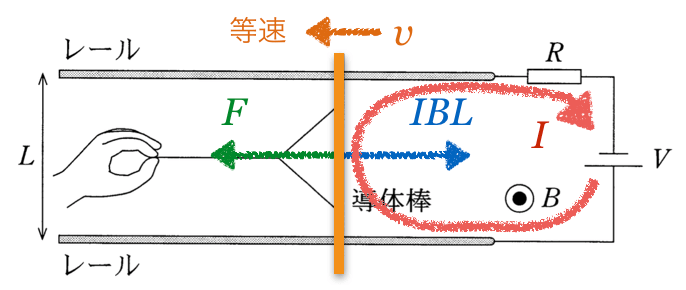
コメント
[…] 2016年度追試第3問A「気柱共鳴」 […]